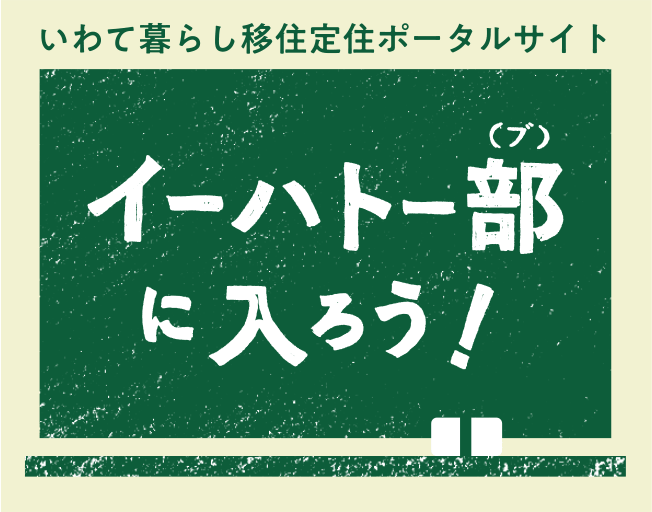岩手県在住作家によるリレー掲載
「ふしぎの国・いわて」アーカイブページ
第3回 三七日の幽霊(2021年9月3日配信)/柏葉幸子
先日お葬式があった。コロナ禍のためお香典だけ届けた。亡くなった人のために泣くこともなく気が抜けたような帰り道だった。
コロナは人との別れも変えていく。いや、葬儀はコロナ前から変わっていたと思う。家族葬がめずらしいことではなくなった。コロナ禍でこれからの葬儀は家族葬が普通になりそうだ。知人、親戚、ご近所まで巻き込む別れから、個々の別れとなる。先輩のことを思った。
癌を患った独身の彼女は、
「生前葬をするの。来てね」
と軽やかに笑った。
気に入りのレストランで仲のいい友を集め、やせ細った彼女は大好きな源氏を朗読した。みな泣くこともなく、思い出話に花を咲かせた。亡くなったと聞いたのは、三か月後だったろうか。
彼女は、自分の一生に自分できっぱりと幕をおろした。
なのに私は、何か解らないことがあると、彼女に聞いてみればいいやと思い、彼女の家の前を通れば、この頃、遊びに来いと電話がないぞと思いかけ、ああ、そうだったと涙ながらに恨めしく思う。
私は、ああ、そうだったを繰り返しながら、ゆっくりと彼女をあきらめていくのだ。こんな別れもある。それはそれでいいが辛い。
子どもの頃のお葬式も思い出した。昔のお葬式はだらだらと続いた。お通夜、お念仏、本葬があり、一七日(ひとなのか)、まず一週間後。二七日、(ふたなのか)三七日(みなのか)まで親戚やご近所の人を集めて供養する。
お通夜、本葬と涙ながらにすませ、一七日、二七日、三七日までくると徐々に涙はない。仏さんに手をあわせはするが、ほとんど宴会だった。そして、やっと四十九日になる。
遠野物語の中に、着物のすそを三角に折り止めたおばあさんの幽霊の話がある。その着物のすそがあたって、いろりのそばに置いてあった丸い炭斗(すみとり)がくるくるまわる。まわる炭斗が目に見えるようで現実味がある。
そして、その家に出戻っていた娘が、ふとんからとびおきて、
「おばあさんが来た!」
と叫ぶ。
同じ幽霊が二度現れる。三七日の供養のあたりの昼間にだ。三七日あたりというのに、私はうなずけてしまう。
おばあさんは先輩のように、きっぱり幕を引いたのではない。心残りがあるから幽霊になって現れる。それは出戻ってきた娘だろうと思う。あの時代に余裕のある家だとしても出戻り娘は肩身が狭かろう。現代だって同じか?そんな娘を残して母親は死ねない。幽霊になって現れる。そしてみんなが落ち着いた頃に、あらためて娘を頼むと念をおすのだ。
遠野物語の幽霊話では、津波の後、海岸に昔の男と幽霊になって現れる妻を、生き残った夫がなじる話を好む人が多いが、私はこの炭斗の幽霊話が好きだ。そりゃ何度でも化けて出たかろうと納得するからだ。遠野物語は本当にあった話として伝承されてきた。私は、遠野のお年寄りたちのように、炭斗の幽霊は本当に二度出たんだと胸をはって言える!
子どもの頃、親戚でお葬式があると、一七日、二七日、三七日と本膳にすわる大人といっしょに私たちもその親戚の家で夕ご飯をごちそうになった。家にもよるが私たち子どももいれたら五十人ぐらいの食事だ。祖母も母もその家で料理を手伝う。家のごはんなど作る暇がない。人参三十本をきざまされる母は、面倒だと文句を言ったが、私は、あの騒がしい食事が好きだった。
「お酒がたりない」
「うちの亭主にもう飲ませねんで」
「わらしゃど(子どもたち)は、こっちで食ってしまえ」
精進料理だから肉や魚など入っていないのに、みんな美味しかった。一族の中で料理上手と評判のおばさんが采配をふるう。お吸い物も白和えもお煮しめも。家で食べるのとは一味も二味も違った。私は野菜料理が豊富で上手な農家レストランのファンだが、子どもの頃のあの興奮を思い出すからだと思う。
さわがしくて、めんどうくさくて、あわただしくて、疲れはてて、でも美味しくて、たまに笑ったりできるようになる。一人じゃない。誰かがそばにいると思えるのだろう。残された人は、半ば強制的に日常にもどる。
だから炭斗の幽霊は三七日すぎにまた現れる。いつもの生活にもどっても、私の心残りを忘れないでほしい。心配な娘を助けてやってほしいと、親戚やご近所の人に念をおし、あらためて頼むのだ。
別れの儀式が一回になり、私のように、いつまでも別れられない者もいる。心残りのある幽霊は、いつ念をおしに現れたらいいのだろう。きっと迷っている。