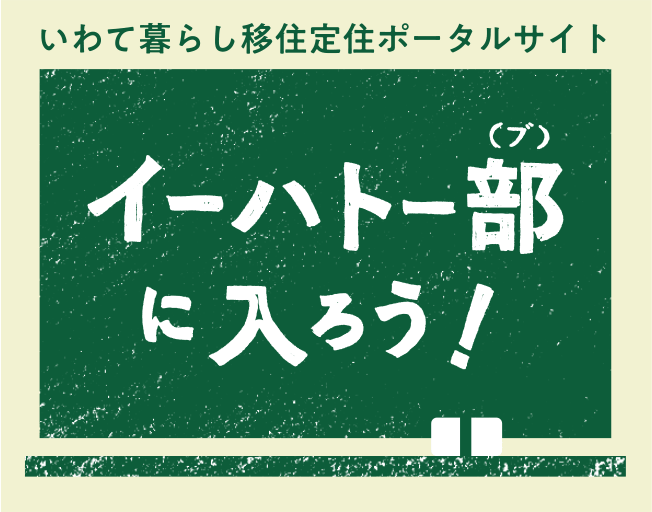岩手県在住作家によるリレー掲載
「ふしぎの国・いわて」アーカイブページ
第12回 花巻駅(2022年6月3日配信)/柏葉幸子
花巻駅の前を通った。この頃、車でしか花巻へ行かないので、花巻駅を見るのはずいぶんと久しぶりだった。ステンドグラスだろうか、きれいな大窓になっていたが、おおむね、私が子どもの頃とそう変わりのない姿だ。改札口を出てすぐの一番線が釜石線。陸橋をこえて一本だけあるプラットホームの、二番線が東北本線の上り線で三番線が下り線だ。こじんまりとした駅だ。新幹線は止まらない。新花巻駅は別にある。
私の花巻駅のイメージは、闇の中に浮かぶ二番線と三番線のプラットホームだ。
子供の頃、父は東京出張というと必ず寝台列車の北星に乗った。今は、岩手と東京は日帰り出張圏だが、あの頃は東京に泊まらなければいけなかった。ホテル代を倹約したのだろう。
花巻駅を夜の九時頃出発だったろうか?茶色のころんとしたボストンバッグがお供だった。子豚みたいだと思ったものだ。父が使わなくなり古びても、家族の誰も捨てられず子豚のバッグは実家にある。
父の出張の見送りに行ったことはない。なのに、闇の中、ライトに照らされて浮かびあがるような花巻駅のプラットホームに、子豚のバッグをさげて一人立つ父の姿を思い描く。他の乗客はいない。いつも一人だ。
父は戦争にいって、シベリア抑留の後花巻へ帰ってきた。二十代前半だったのだろう。
「鉄砲を撃ったのか?」
と、誰かが聞くと、
「図面を引いていた」
と言った。
父の部隊は空港を造らなければいけなかったらしい。図面を引ける人がいなくて、満州の工業高校を出た一番若かった父が図面を引いたのだそうだ。
「その図面に俺の判を押したわけだ」
と自慢げだった。
その判のせいで、花巻へ帰ってすぐGHQから呼び出しがあった。祖母は、
「どったな(どんな)、わるいごとしてきたんだべ!」
と泣いたそうだ。
「真夜中に俺一人を乗せるために、花巻駅に立派な列車が止まった」
不安と興奮がいりまじった若い父が見えるようだ。父は、そのまま何事もなく帰ってきたのだが、その話のせいで、花巻駅のプラットホームで北星を待つ父のイメージは、いつも一人だ。
私は講談社の児童文学新人賞をいただいて「霧のむこうの不思議な町」という本でデビューさせていただいた。その時の選考委員だった佐藤さとる先生に、上京するたびに、いろいろとお話をうかがうことができた。
「遠野と花巻で育ちました」
というと、
「すごい所で育ったね。きっと、いいお話をたくさん書けるよ」
と言ってくださった。
「賢治は読むの?」
と聞かれて、いいえと首をふった私に先生は苦笑いをしたようだった。
なんども先生の書斎でお話を聞いたが、賢治さんのことは出てこなかったと思う。
先生の自伝で、戦後すぐ家族で北海道へ引っ越した時のことを読んだ。青函連絡船に乗るために夜行列車で青森まで行ったそうだ。あの頃の列車だ。四人掛けの固いシートに、ノッポの先生は体を折り曲げるようにして乗っていたのだろう。
夜中に列車が止まって目がさめると、真っ暗なプラットホームに花巻の表示だけ見えたそうだ。『ああ!賢治の町だ』と思ったとあった。
降りる人もいなかったろう闇に浮かぶプラットホーム。そこに停車している列車。その中に、引っ越し先での生活の期待と不安。また賢治さんの童話への思いを胸に秘めた若い先生がいたのだ。
先生はきっと賢治さんが好きだったのだろう。でも、ほとんど読まないといった私には、何も話してはくださらなかった。せっかく花巻で育ったのに、困った子だと私を見ていたのだろう。田舎からのこのこ出てきた私に親切にしてくださったのは賢治の町の子だと思ったからだ。
駅というのは、通勤や通学に使う生活に密着した場所でもあり、旅へ出る不安と期待と興奮が渦巻く場所でもある。
私の花巻駅のイメージは、いつも闇に浮かぶプラットホームだ。そこに父がいて先生がいる。