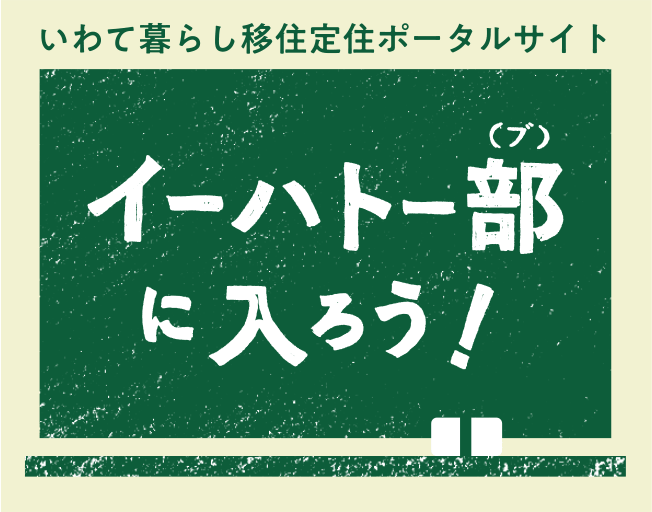岩手県在住作家によるリレー掲載
「ふしぎの国・いわて」アーカイブページ
第7回 文士劇(2022年1月7日配信)/柏葉幸子
盛岡の師走の風物詩だそうだ。盛岡文士劇というのがあることは知っていた。
「出るの?」
と、東京の仕事先で聞かれたこともある。まさか!と首をふった。私が文士?私が書くのは子どもの本だし、関係ないと思っていた。テレビで放映することもあるのに見たこともなかった。いくらなんでも、テレビぐらい見ておくべきだった。
平成二十五年の文士劇に出ませんかとお誘いがあった。その二年前に東日本大震災があって、私でもできることはなんでもしなければ!という思いにかられていた。それに震災の後、復興支援として岩手の作家たちが短編を一篇ずつ寄付してアンソロジーを出版し、印税を被災地に送った。その関わりで、岩手の物書きの人たちを知った。私は、それまで、岩手にいながら同じ職業の人をほとんど知らなかった。高橋克彦先生をはじめ、皆様、優しく頼もしく、何もわからない私でもなんとかなりそうに思えた。
「はい」
と答えてしまった。
私の文士劇のイメージは、遠藤周作の大根座なのに―。
私が中学生の頃、父が週刊朝日を読んでいた。私も父や母が読んだ後読んだ。両親も私も遠藤周作の狐狸庵日記のファンだった。そこで、大根座という文士劇の話を読んだ。お腹をかかえて転げまわって笑った。文士劇とは、セリフが飛んでしどろもどろになるのは当たり前で、芝居の筋があっちへ行ったりこっちへ来たりしながら観客に笑ってもらうものなのだという固定観念が私にできあがっていた。
なのに盛岡文士劇は、お稽古が週三日、二か月間つづく。地元のテレビ局のアナウンサーたちは、夕方のニュースを読むや否やお稽古に飛んでくる。(アナウンサーも文士劇に出演する)こりゃ大変だと、あわてて締め切りをのばしてもらった。その時に気がつけばよかったのに―。
演目は「赤ひげ」。私は、若い医者の母親役でセリフは二行だった。なのに、その二行がなかなか覚えられない。一か月もたつと、
「あいつは今だに台本を離せない」
とささやく声がする。身がちぢむ思いだ。
皆様私の何十倍もセリフがあるのに、セリフ覚えがいい。聞くとたいていの人が学生時代は演劇部だった。覚えるこつがあるのだろうか。セリフが飛ぶなどもってのほかだ。
脚本は平成十三年からの道又力氏、演出は秋田のわらび座から安達和平先生が通ってくる。
「はい、このセリフ!涙を誘うねぇ!」
泣かすのですか?笑わせるのではなく!うろたえているのは私だけだ。もう商業劇団ののり。実際、観客は泣きました。完成度が半端ない。
私が参加させていただくものではないと、つくづく思ったのに、いろいろあって次の年の「巌窟王」まで出演させていただいた。
「何の役?」
と聞かれて、
「名前ないの。とにかく悪漢の妻」
と答えたら、巌窟王好きの編集者が「ときこ」だろうと調べてくれた。
衣装に金色と赤が基調の派手派手な私サイズのローブデコルテを作ってもらった。下着にパニエまであった。あまりに申し訳なくて買い取りましょうかと申し出たが、大丈夫だと断られた。
それを着て舞台でパニエを踏みそうになりながらワルツを踊った。もうこれで最後だと思ったので担当の編集者たちを全員呼んだ。みんな、たいへん面白がってくれた。私のワルツを!冷や汗もあそこまでくると凍り付く。
私史上、なんとも派手やかな二年となった。誘っていただいて感謝している。
先日、コロナでお休みしていたが二年ぶりに文士劇が復活した。いつもは内館牧子先生や井沢元彦先生が東京から出演してくださったりするが、今年は岩手在住作家だけの舞台だ。
初めて観客としてみせていただいた。盛岡劇場は満員御礼のにぎわいで、みなさん待ちかねていた再開だ。現代劇の「アイは猫である」と時代劇「人間万事金の世の中」どちらも熱演で、とにかく笑えた。
笑えてよかった。観客全員そう思ったのだと思う。ここ二年コロナで自粛で息をひそめるような生活を強いられていた。コロナ第六波が来る前のエアポケットみたいな平安な一時期だ。楽しかった、面白かった。そして、クリスマスと大晦日になだれ込む。文士劇の皆様にただ感謝だ。
お正月のお屠蘇には「巌窟王」の衣装にちなんで「ときこ」と名付けた赤と金のガラスのぐい呑みを使うことにしている。